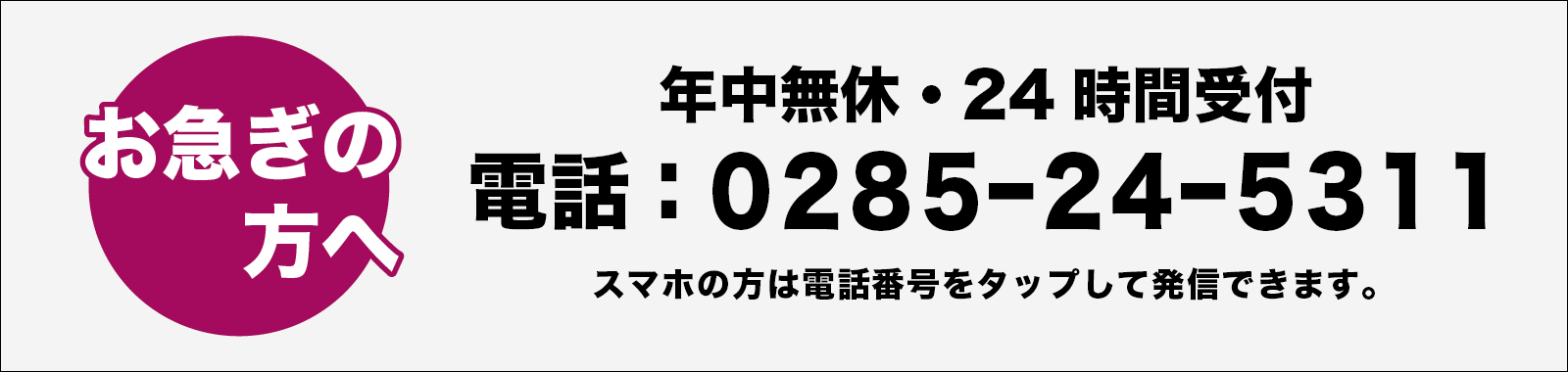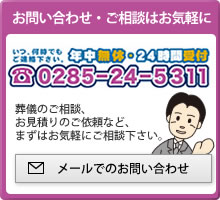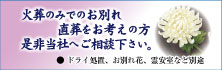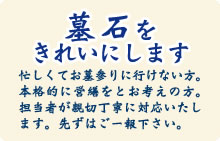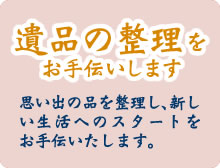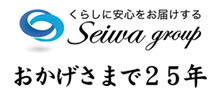誠和葬祭
葬儀豆知識No.290 「儀式で渡される清めの塩の正しい使い方編」清め塩を使う場所
2019年7月22日 ニュース
※ 玄関をまたぐ前に行う 清めの塩は、家に帰ってきてすぐに、玄関をまたぐ前に行います。 人に見られたくない・マンションの共用部を汚したくない等、玄関の内側で清めをする方もいますが、この場合は穢れが家の中に入ってしまいます …
葬儀豆知識No.289 「儀式で渡される清めの塩の正しい使い方編」 清め塩とは
2019年7月21日 ニュース
お葬式に参列すると、会葬礼状などと一緒に塩を渡されることがあります。この塩は清めの塩といい、身体を清めるために使います。 清め塩とは、もともと神道で用いられる儀式であり死を穢れとして扱っているため、この穢れを祓うために塩 …
葬儀豆知識No.288 「盆堤灯に家紋を入れる必要はある?編」 家紋入堤灯の手配はお早めに
2019年7月20日 ニュース
新盆の最高の供物となる白堤灯へ家紋を入れるのは、ほとんどが職人の手作業です。 家紋入り堤灯の注文はオーダーメイド扱いのため、家紋の最終確認の連絡があってから作りはじめます。 家紋入りの完成日数は約10~14日間くらいかか …
葬儀豆知識No.287 「盆堤灯に家紋を入れる必要はある?編」 新たに家紋を作ることもできる
2019年7月19日 ニュース
家紋は、自分の代から作ることもできます。 家族や親戚などと相談しながら家紋を選ぶのも今風で一つの方法でしょう。 最近ではオリジナルの家紋を作成しているサービスもあります。 皇室の御印のように故人の持ち物にシンボルを入れる …
葬儀豆知識No.286 「盆堤灯に家紋を入れる必要編」 家紋がわからない場合
2019年7月18日 ニュース
新しく堤灯を作るなら、家紋を入れて新盆を迎えるのが正式と言えます。 家紋がわからない場合は、家の柱と梁の装飾や男性の羽織袴、女性の第一礼装留袖や喪服などを確認してみましょう。 また、先祖のお墓に彫ってあることもあります。 …
葬儀豆知識No.285 「新盆の堤灯に家紋が付いている理由編」 盆堤灯の飾り方
2019年7月17日 ニュース
一般的な白堤灯はローソクの火を灯せるようになっていますが、火事の危険が伴うため火は入れずお飾りとしているところもあります。 祖先のための絵柄の入った盆堤灯は、精霊棚または盆棚や仏壇の両脇に一対、二対と飾ります。 飾るスペ …
葬儀豆知識No.284 「新盆の堤灯に家紋が付いている理由編」 新盆に必要な [白堤灯]
2019年7月16日 ニュース
新盆には通常、祖先のために飾る絵柄の入った盆堤灯のほかに、新盆用の白堤灯を飾ります。 白堤灯は、四十九日を済ませ初めて帰ってくる故人の霊が家への帰路を迷わないための目印となるものです。 祖先のために飾る絵柄の入った盆堤灯 …
葬儀豆知識No.283 「新盆の堤灯に家紋が付いている理由編」 盆堤灯は先祖が迷わず帰るための目印
2019年7月15日 ニュース
お盆で堤灯を飾る風習のある地域では絵柄の入った堤灯は祖先の霊に、白い堤灯は新盆を迎えた故人にと区別して使用します。 盆堤灯は、お盆に家に帰ってくる先祖や故人の霊が迷わないように目印として飾られます。 ただし、地域によって …
葬儀豆知識No.282 「会社関係者の家族葬でのマナー編」 香典は渡さず早めに引き上げる
2019年7月14日 ニュース
ご自宅への弔問では、家族葬なので香典や供花・供物の持ち込みも控えるのがマナーです。 ご遺族とのお付き合いの深さにもよりますが、あまり長居はせずに辞去しましょう。 ご遺族は葬儀を終えて疲れていますし、葬儀が終わった後も色々 …
葬儀豆知識No.281 「会社関係者の家族葬でのマナー編」 伺うなら家族葬から一週間以内に
2019年7月13日 ニュース
弔問に訪れる場合は、葬儀から間を置かずに伺うようにします。 なるべく、伺う期間は葬儀から一週間以内が目安です。 ご遺族は家族葬であっても葬儀後に弔問客が訪れる事は想定しています、「しばらくしてご遺族が落ち着いてからのほう …